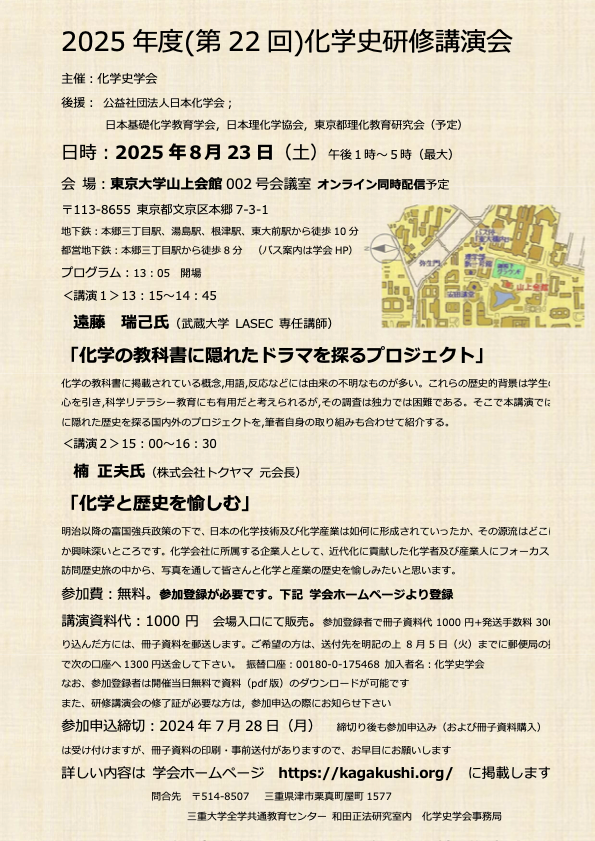ギースシンポジウム(2/28)「アーリーキャリアの声から――アカデミアのジェンダー平等を再構築する」
化学史学会が加盟しているGEAHSSより,公開シンポジウムのご案内が届きましたので,会員のみなさまにお知らせ致します。(事務局)
**
2月28日(土)、人文社会科学系学協会男女共同参画推進連絡会(GEAHSS)主催の公開シンポジウムを開催いたします。(企画:日本社会福祉学会)
「アーリーキャリアの声から――アカデミアのジェンダー平等を再構築する」
日時: 2026年2月28日(土)13:00-16:30
場所: ZOOMによるオンライン開催
参加無料(※事前登録制、先着300名)
▼お申込みはこちらから
https://x.gd/fMM3B
申込締め切り2026年2月26日
▼詳細はこちらをご確認ください。
https://geahssoffice.wixsite.com/geahss/single-post/20260228
ポスター(pdf)